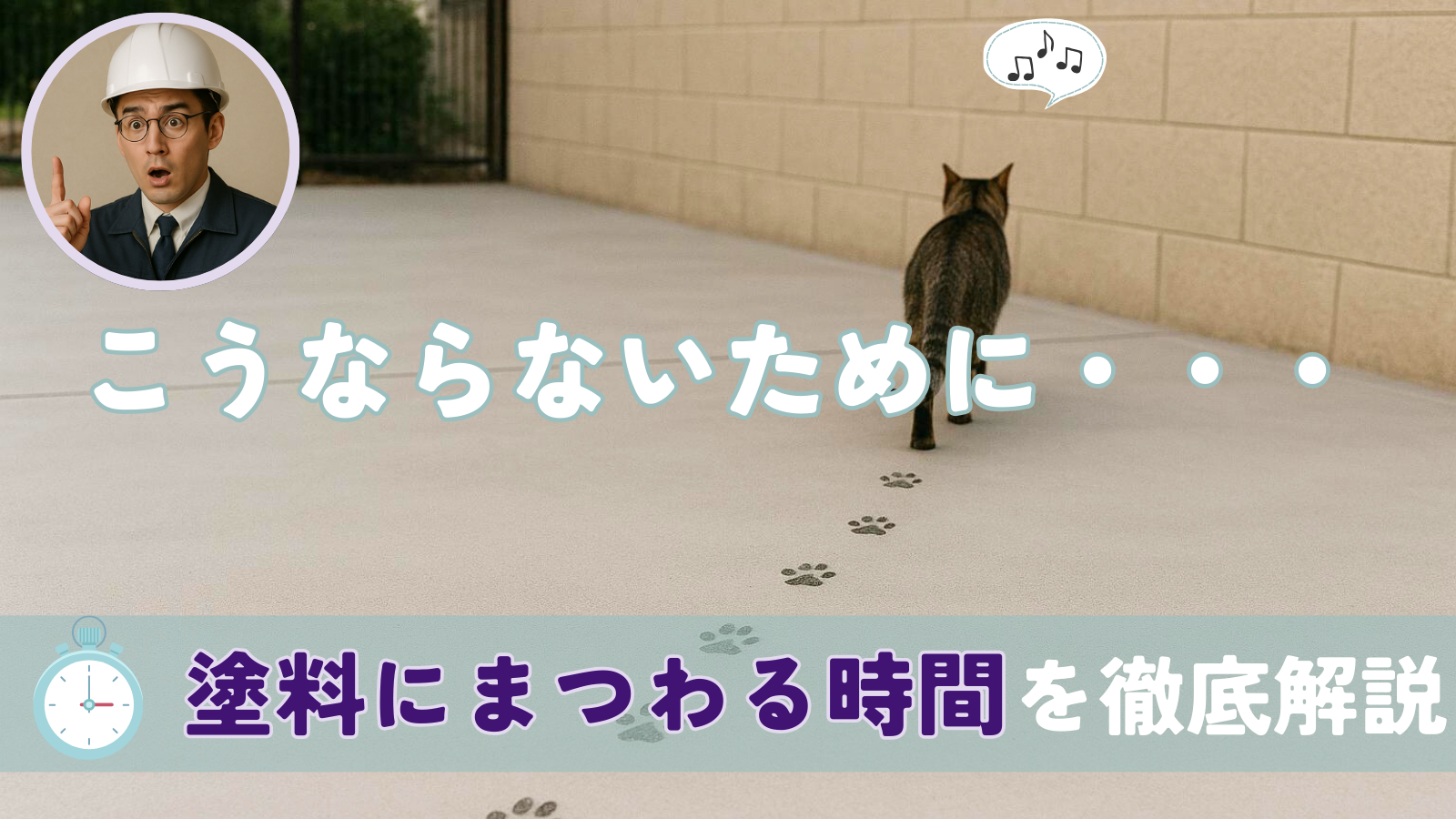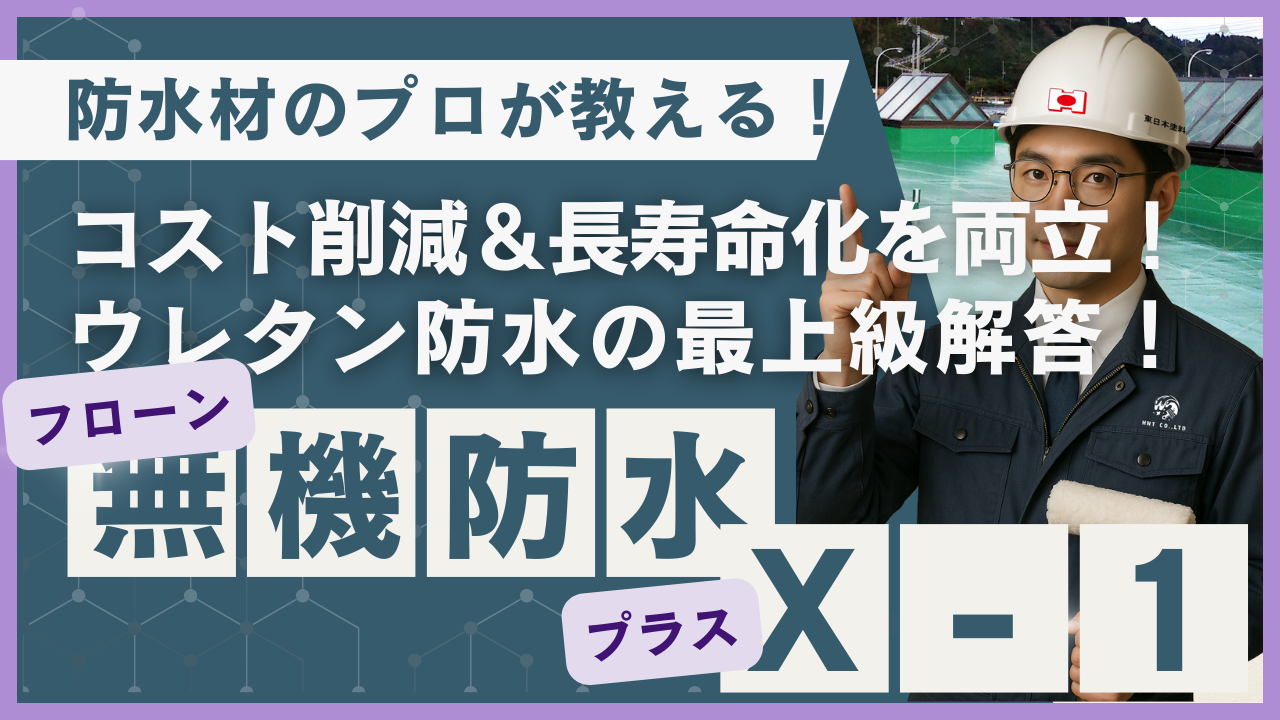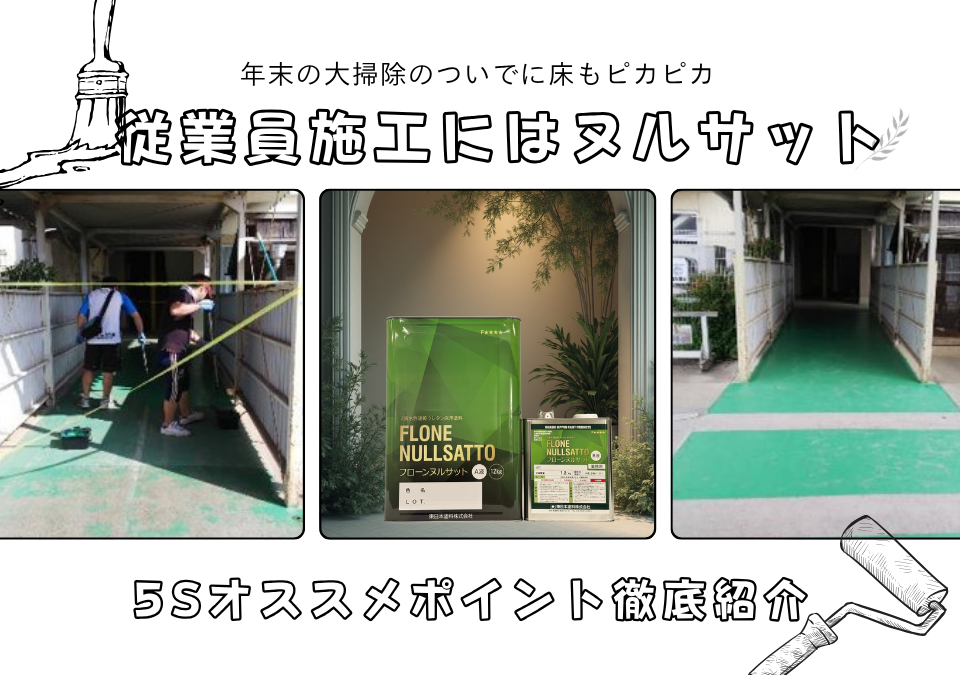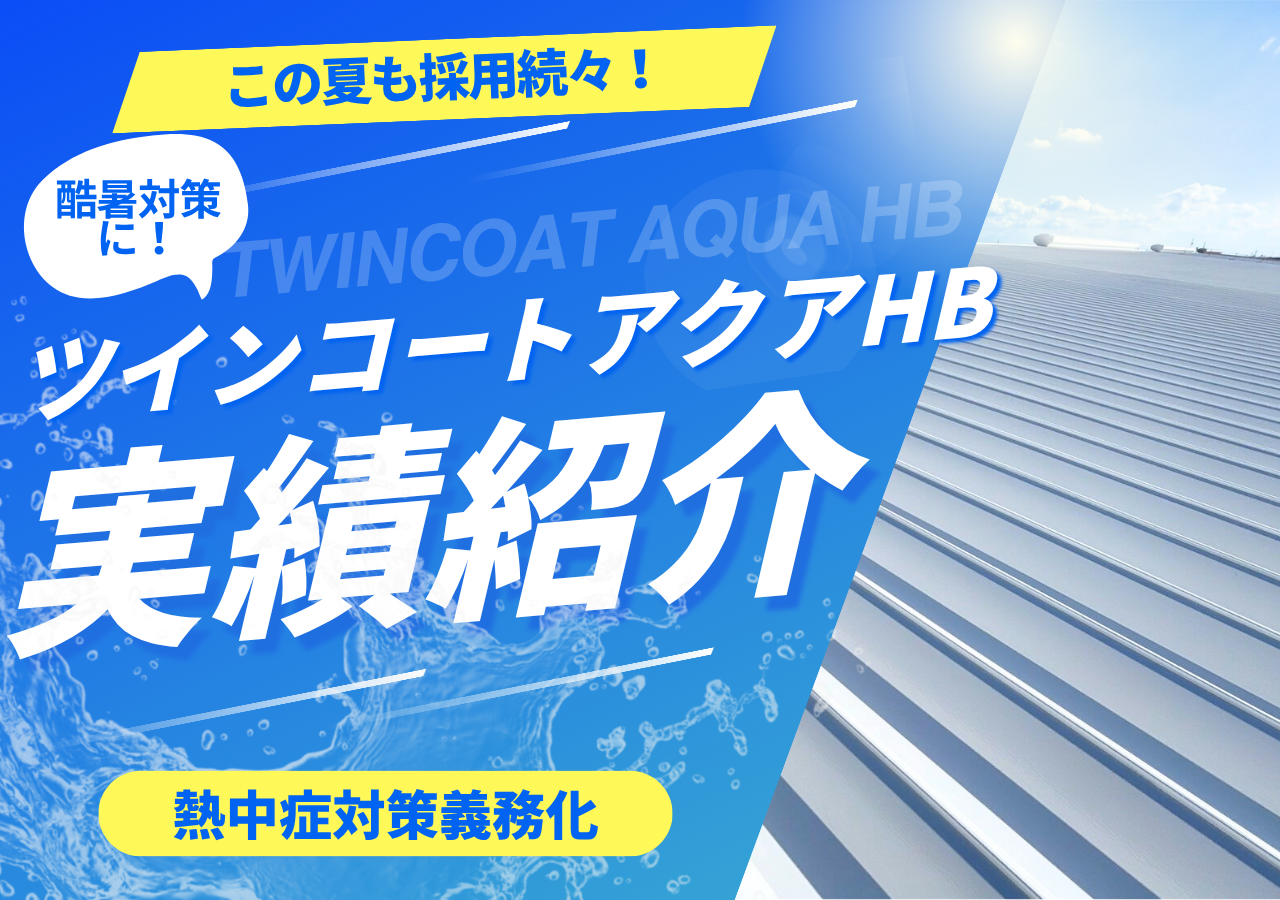塗料の基礎知識
2021/04/14
.jpg)
「防水材が乾かない!なんで?どうしたらよかったの(泣)?」~防水材不具合シリーズ第2弾~
管理者用.jpg)
「防水材が乾かない!なぜ?」
というお問合せをよくいただきます。

防水材の硬化不良事例1
このような状況を「硬化不良」と言います。
もうすぐ梅雨(気が早い)。
梅雨前にしっかりと防水材を塗布し、雨漏りを防ぎたい今日この頃。
(デジャヴ)
そこで、本日は、防水材の不具合シリーズ第2弾!
「防水材の硬化不良」の原因や対策、対処法について、
たっぷりと説明いたします。
まずは、「防水材の硬化不良」の原因から見ていきましょう!
原因1: A液とB液の混合比が適正ではなかった
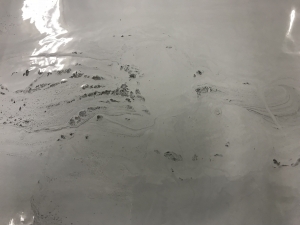
防水材の硬化不良事例2
現場の失敗例
「だいたいの量を混ぜればいいんでしょ?大丈夫、いつもこうやってる!」
「秤がなかったし、計るの面倒だから目分量でやっちゃった」
「1:1って書いてあったから、同じ量を混ぜたよ」
硬化不良の原因
2液塗料の場合、A液とB液の反応で硬化します。
しかし、配合比が適正でないと、正しく反応せず、
硬化不良を起こしてしまいます。
対策
必ず計量器を使って重さを計って混合しましょう。
目分量ですと、どちらかが多くなったり少なくなったりして、
ただしく反応しないことがあります。
また、必ず「重さ」を計ってください。
体積比ではないので、注意が必要です。
原因2: 正しく撹拌ができていなかった
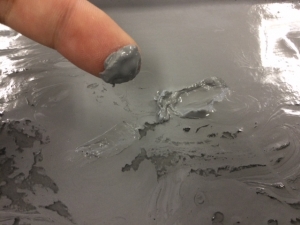
防水材の硬化不良事例3
現場の失敗例
「電動撹拌機?なんて持ってないから、棒で混ぜたよ」
「軽く混ぜたら簡単に混ざった!硬化剤の色も消えたし、大丈夫だと思って・・・」
硬化不良の原因
先程も原因1で述べた通り、
2液の塗料は、A液とB液の反応で硬化します。
そのため、しっかりと混ざっていないと反応が起きず、硬化しません。
また、棒で混ぜただけですと、十分に撹拌することができず、
硬化不良を起こしてしまいます。
また、電動攪拌機を使ったとしても、撹拌時間が短い場合、
ムラができてしまい、反応が起きず、これも硬化不良の原因となります。
上の写真をご覧ください。
撹拌不足でA液とB液が混ざっていないと、
上の写真のように、分離した状態になってしまいます。
対策
必ず電動撹拌機を使用!
そして充分な時間撹拌してください。
また、攪拌後でも、缶の側面に残ってしまった材料でも、
硬化不良になる恐れがあるため、使用しないでください。
原因3: 過度な希釈をした・シンナーを間違えた
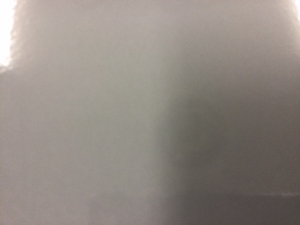
防水材の硬化不良事例4(わかりづらくてすみません)
現場の失敗例
「どろどろしていてとても塗りづらい!だから希釈したよ」
「どのくらい・・・・?うーん、塗りやすくなるくらい入れたよ」
「何のシンナーだって?わからないけどアルコールが入ってるシンナーだと思うよ」
硬化不良の原因
弊社の防水材は基本的に希釈することをお勧めしておりません。
希釈せずにお使いいただいております。
しかしながら、お客様からは、
「粘度が高いから塗りづらい。もっとさらさらにしたい」
というお声をよくいただきます。
その際は、シンナーでの希釈とお答えしておりますが、
その希釈量が多かったり、おすすめしているシンナーではないものを使用すると、
まったく乾かず、硬化不良が起こってしまうのです。
対策
A液・B液総重量の1~2%以下で希釈してください。
これ以上多い場合、乾燥に非常に時間がかかりますが、
時間を置けば、乾燥はします。
しかし、長時間水分にも当てずに、
また、ちり・ホコリを防ぎながら乾燥させるのは難しいと思いますので、
基本的には入れ過ぎないほうがよいでしょう。
また、アルコールを含むシンナーでの希釈は避けてください!
必ずウレタンシンナー(弊社製品で言うと「トップ14シンナー」)を
ご使用ください。
「塗料用シンナー」もお使いいただけませんので、ご注意ください!
原因4: 乾く前に水分にあたってしまった
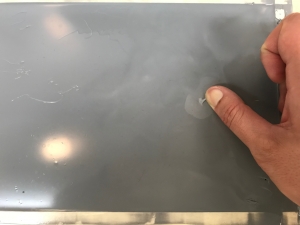
現場の失敗例
「急いでいたから塗装後の天気を確認しないで施工したら、雨が降ってきた!」
「夜中に結露したみたい・・・その後、全然乾かない!」
硬化不良の原因
施工直後に雨や結露などの水分の影響を受けてしまうと
硬化不良が起きてしまいます。
また、施工中の汗が落ちてしまうだけでも
硬化不良の原因となりますので、ご注意ください。
対策
乾燥時間中の水分は避けましょう。
雨が降る前の施工、寒暖差が激しく結露が出る可能性がある時期、
また、汗が落ちないような工夫などを心がけましょう。
原因5: 気温が低く、乾燥に時間がかかっている
現場の失敗例
「5℃以上はあったけど寒い日に施工したら、全然乾かない!」
硬化不良の原因
低温時は乾燥に非常に時間がかかります。
そのため、低温が原因のみであれば、
乾燥時間を延ばせば硬化します。
対策
先述のとおり、乾燥時間を延ばせば硬化はします。
しかしながら、先述の通り、
長時間水分にも当てずに、
また、ちり・ホコリを防ぎながら乾燥させるのは難しいと思いますので、
低温時の施工は避けた方がよいでしょう。
また、「そんなに待てない!」という場合には、
防水材専用の硬化促進剤を使用することをおすすめいたします。
弊社製品では、「フローン防水材硬化促進剤」。
A液とB液を混合する際に、使用するものです。
こちらは、冬型・低温時のみ使用可能となっております。
夏型や暖かい時期に使用してしまうと、
可使時間が非常に短くなってしまいますので、
使用はお控えください。
さて、防水材の硬化不良の原因はお分かりいただけたでしょうか?
「いや、待て、既に硬化不良が起こってしまってるんだ!」
「待てど暮せど乾かない・・・目の前のこれ、どうしよう?」
では、硬化不良が起きてしまったらどうしたらよいのでしょうか?
下記に、処理方法をご紹介いたします!
硬化不良発生時の処理方法
原因1~2の場合
原因3の場合(アルコールを含む溶剤で希釈した場合)
原因4の場合
下記に、今回の内容を一覧表にして、まとめておきますね。
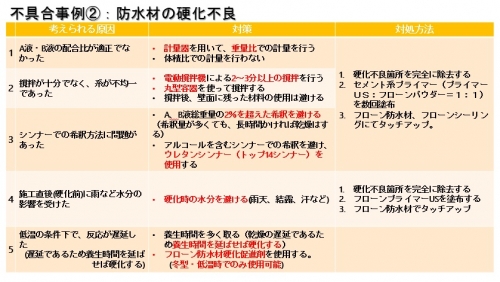
せっかく時間とコストをかけて防水工事をするのですから、
不具合なく、キレイに仕上げたいですよね。
ぜひ、ご参考いただけますと幸いです。
それでは、不具合のない美しい防水材ライフ(?)をお過ごしください!
というお問合せをよくいただきます。

防水材の硬化不良事例1
このような状況を「硬化不良」と言います。
もうすぐ梅雨(気が早い)。
梅雨前にしっかりと防水材を塗布し、雨漏りを防ぎたい今日この頃。
(デジャヴ)
そこで、本日は、防水材の不具合シリーズ第2弾!
「防水材の硬化不良」の原因や対策、対処法について、
たっぷりと説明いたします。
まずは、「防水材の硬化不良」の原因から見ていきましょう!
原因1: A液とB液の混合比が適正ではなかった
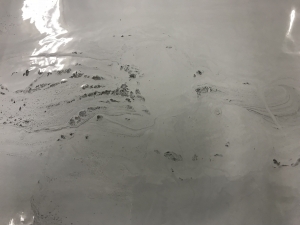
防水材の硬化不良事例2
現場の失敗例
「だいたいの量を混ぜればいいんでしょ?大丈夫、いつもこうやってる!」
「秤がなかったし、計るの面倒だから目分量でやっちゃった」
「1:1って書いてあったから、同じ量を混ぜたよ」
硬化不良の原因
2液塗料の場合、A液とB液の反応で硬化します。
しかし、配合比が適正でないと、正しく反応せず、
硬化不良を起こしてしまいます。
対策
必ず計量器を使って重さを計って混合しましょう。
目分量ですと、どちらかが多くなったり少なくなったりして、
ただしく反応しないことがあります。
また、必ず「重さ」を計ってください。
体積比ではないので、注意が必要です。
原因2: 正しく撹拌ができていなかった
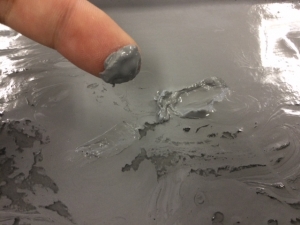
防水材の硬化不良事例3
現場の失敗例
「電動撹拌機?なんて持ってないから、棒で混ぜたよ」
「軽く混ぜたら簡単に混ざった!硬化剤の色も消えたし、大丈夫だと思って・・・」
硬化不良の原因
先程も原因1で述べた通り、
2液の塗料は、A液とB液の反応で硬化します。
そのため、しっかりと混ざっていないと反応が起きず、硬化しません。
また、棒で混ぜただけですと、十分に撹拌することができず、
硬化不良を起こしてしまいます。
また、電動攪拌機を使ったとしても、撹拌時間が短い場合、
ムラができてしまい、反応が起きず、これも硬化不良の原因となります。
上の写真をご覧ください。
撹拌不足でA液とB液が混ざっていないと、
上の写真のように、分離した状態になってしまいます。
対策
必ず電動撹拌機を使用!
そして充分な時間撹拌してください。
また、攪拌後でも、缶の側面に残ってしまった材料でも、
硬化不良になる恐れがあるため、使用しないでください。
原因3: 過度な希釈をした・シンナーを間違えた
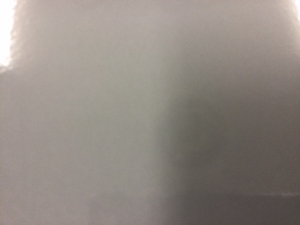
防水材の硬化不良事例4(わかりづらくてすみません)
現場の失敗例
「どろどろしていてとても塗りづらい!だから希釈したよ」
「どのくらい・・・・?うーん、塗りやすくなるくらい入れたよ」
「何のシンナーだって?わからないけどアルコールが入ってるシンナーだと思うよ」
硬化不良の原因
弊社の防水材は基本的に希釈することをお勧めしておりません。
希釈せずにお使いいただいております。
しかしながら、お客様からは、
「粘度が高いから塗りづらい。もっとさらさらにしたい」
というお声をよくいただきます。
その際は、シンナーでの希釈とお答えしておりますが、
その希釈量が多かったり、おすすめしているシンナーではないものを使用すると、
まったく乾かず、硬化不良が起こってしまうのです。
対策
A液・B液総重量の1~2%以下で希釈してください。
これ以上多い場合、乾燥に非常に時間がかかりますが、
時間を置けば、乾燥はします。
しかし、長時間水分にも当てずに、
また、ちり・ホコリを防ぎながら乾燥させるのは難しいと思いますので、
基本的には入れ過ぎないほうがよいでしょう。
また、アルコールを含むシンナーでの希釈は避けてください!
必ずウレタンシンナー(弊社製品で言うと「トップ14シンナー」)を
ご使用ください。
「塗料用シンナー」もお使いいただけませんので、ご注意ください!
原因4: 乾く前に水分にあたってしまった
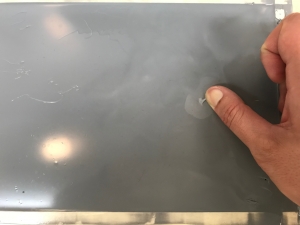
現場の失敗例
「急いでいたから塗装後の天気を確認しないで施工したら、雨が降ってきた!」
「夜中に結露したみたい・・・その後、全然乾かない!」
硬化不良の原因
施工直後に雨や結露などの水分の影響を受けてしまうと
硬化不良が起きてしまいます。
また、施工中の汗が落ちてしまうだけでも
硬化不良の原因となりますので、ご注意ください。
対策
乾燥時間中の水分は避けましょう。
雨が降る前の施工、寒暖差が激しく結露が出る可能性がある時期、
また、汗が落ちないような工夫などを心がけましょう。
原因5: 気温が低く、乾燥に時間がかかっている
現場の失敗例
「5℃以上はあったけど寒い日に施工したら、全然乾かない!」
硬化不良の原因
低温時は乾燥に非常に時間がかかります。
そのため、低温が原因のみであれば、
乾燥時間を延ばせば硬化します。
対策
先述のとおり、乾燥時間を延ばせば硬化はします。
しかしながら、先述の通り、
長時間水分にも当てずに、
また、ちり・ホコリを防ぎながら乾燥させるのは難しいと思いますので、
低温時の施工は避けた方がよいでしょう。
また、「そんなに待てない!」という場合には、
防水材専用の硬化促進剤を使用することをおすすめいたします。
弊社製品では、「フローン防水材硬化促進剤」。
A液とB液を混合する際に、使用するものです。
こちらは、冬型・低温時のみ使用可能となっております。
夏型や暖かい時期に使用してしまうと、
可使時間が非常に短くなってしまいますので、
使用はお控えください。
さて、防水材の硬化不良の原因はお分かりいただけたでしょうか?
「いや、待て、既に硬化不良が起こってしまってるんだ!」
「待てど暮せど乾かない・・・目の前のこれ、どうしよう?」
では、硬化不良が起きてしまったらどうしたらよいのでしょうか?
下記に、処理方法をご紹介いたします!
硬化不良発生時の処理方法
原因1~2の場合
- 硬化不良個所を完全に除去する
- フローンプライマーUS+フローンパウダーを1:1で配合したものを数回塗布
- フローン防水材、フローンシーリングでタッチアップ
原因3の場合(アルコールを含む溶剤で希釈した場合)
- 硬化不良個所を完全に除去する
- フローンプライマーUS+フローンパウダーを1:1で配合したものを数回塗布
- フローン防水材、フローンシーリングでタッチアップ
原因4の場合
- 硬化不良箇所を完全に除去する
- フローンプライマーUSを数回塗布
- フローン防水材でタッチアップ
下記に、今回の内容を一覧表にして、まとめておきますね。
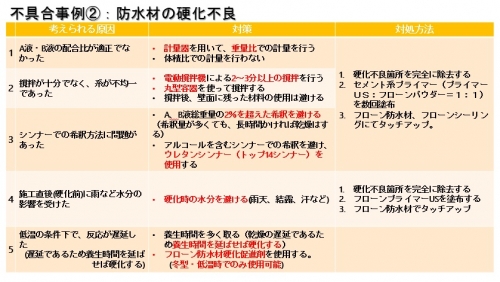
せっかく時間とコストをかけて防水工事をするのですから、
不具合なく、キレイに仕上げたいですよね。
ぜひ、ご参考いただけますと幸いです。
それでは、不具合のない美しい防水材ライフ(?)をお過ごしください!

.jpg)