弊社製品について
2021/01/20
.png)
「断熱コートシリーズ」は冬でも効果があるってご存知でしたか?~「断熱コートシリーズ」の「保温性」~
管理者用.png)
突然ですが、断熱コートシリーズと言えば??
「断熱」
「夏涼しい!」
「省エネ!」
「部屋の中の温度が上がるのを防ぐ!」
「防音!」
「結露抑制!」
「白い!」
「厚み」
「あの独特な手触り!」(←?)
弊社内では、上記のような答えが返ってきました。
上記はすべて、断熱コートシリーズの特長を表しています。
しかし!
実は断熱コートシリーズには「保温性」という特長があるのをご存知ですか?
今日は、この「保温性」に着目して、説明していきますね。
「保温性」というと「冬」というイメージですが、
「結露抑制」と同様、冬期に効果を発揮するんです。
一般の塗料は、「温まりやすく冷めやすい」のですが、
断熱コートシリーズは、「温まりにくく冷めにくい」という特長があります。
これは、どういうことか、というと、
「温まりにくく冷めにくい」つまり「保温性が高い」ということになるんです。
「温まりにくいのに保温性?」
と思われる方もいらっしゃると思いますが、
サーモ機能付きの水筒を思い出してください。
「温かいものは温かいまま、冷たいもの冷たいまま」ですよね?
中の飲料などが同じ温度を維持する、ということになります。
これこそ、保温性なのです!
つまり、同じ温度を維持するということは保温効果が高い!ということなんです。
だからこそ、「温まりにくく冷めにくい」というのは
「保温性が高い」ということになります。
ここで、断熱コートシリーズのイメージ図を見てみましょう。
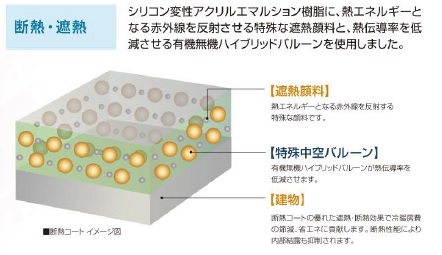
断熱コートシリーズには、「特殊中空バルーン」というものが使われています。
この「特殊中空バルーン」が、熱伝導率を低減させる働きをしています。
どういうことかというと、
このバルーンが熱を伝えない空気の層を作り、
この空気の層、つまり気泡が保温性を高めているのです。
この気泡の中の空気は温まると、その熱を保つ性質があります。
では、この「特殊中空バルーン」が入っている塗料と、
入っていない塗料では、どのくらい違うのでしょうか?
下記をご覧ください。
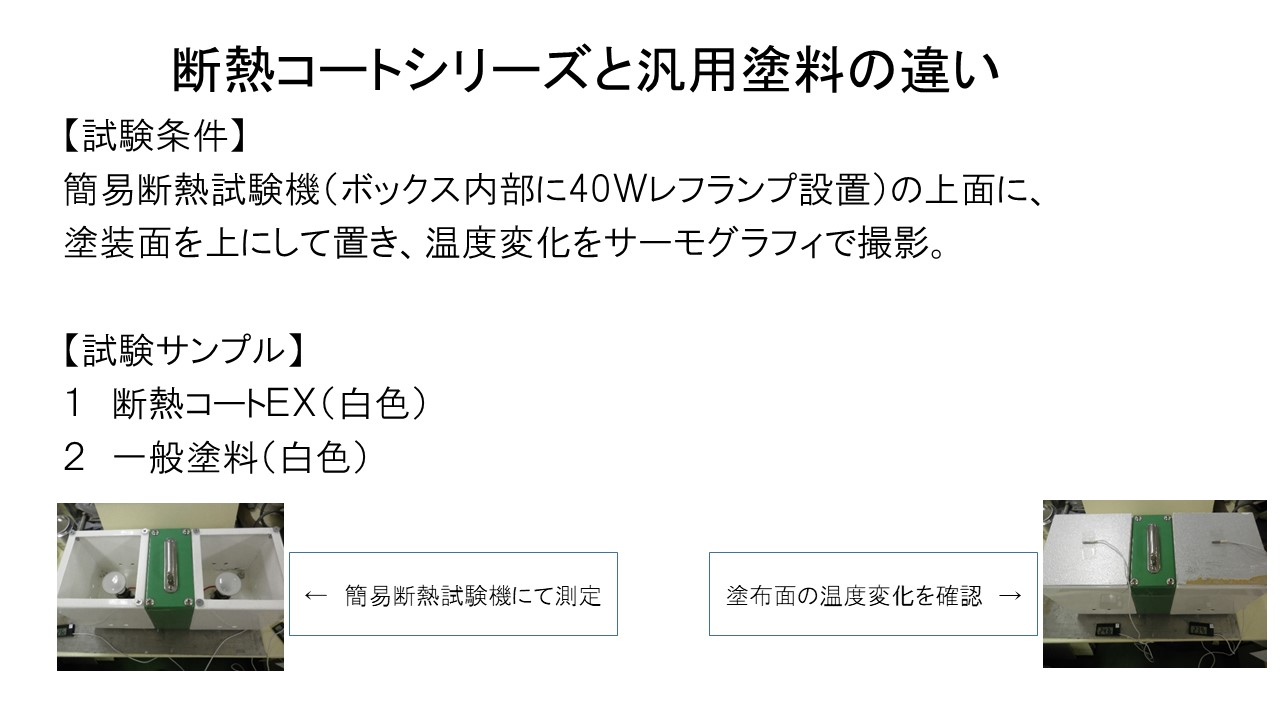
上記のような条件と装置で実験してみました。
すると、下記のような結果が得られました。
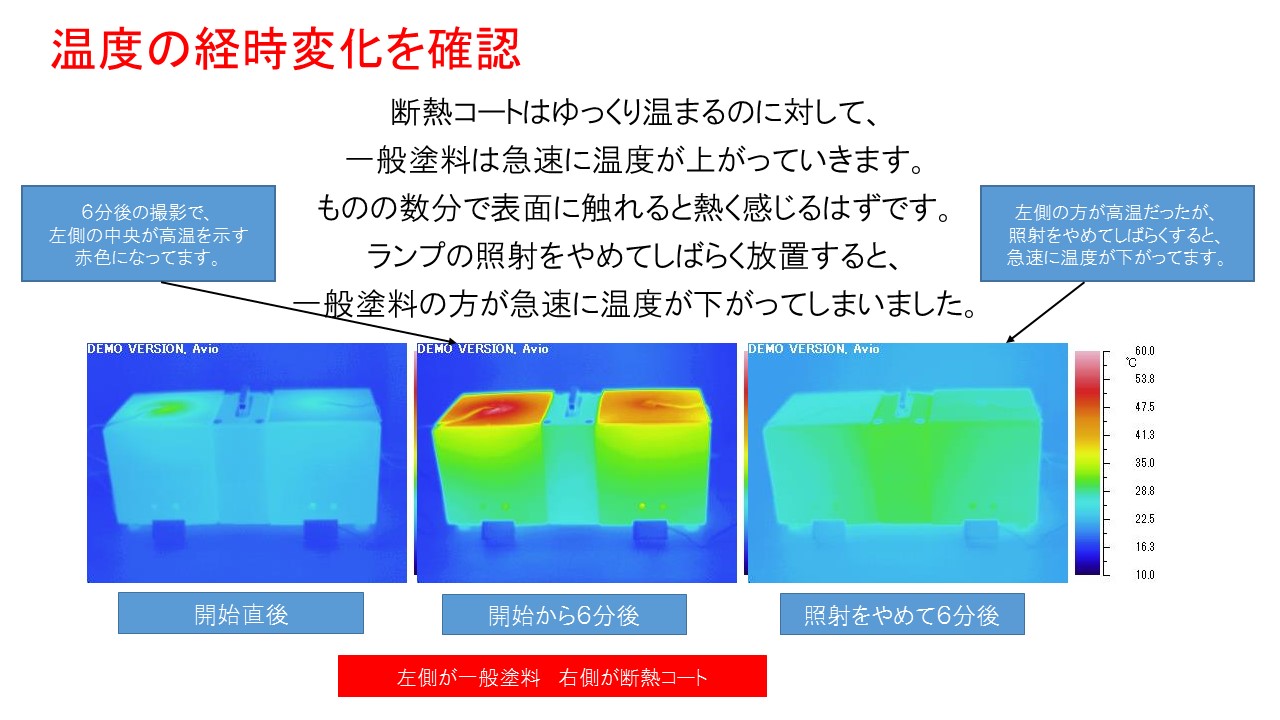
このことから、断熱コートEXを塗布したものは、ゆっくりと温まり、
ランプの照射をやめても、急激な温度低下が見られないということがわかります。
つまり、一般塗料と比較しても、「保温性が高い」ということが分かります。
「実験だけじゃなくて、実際はどうなの?」
と思われる方も多いと思います。
それでは、断熱コートシリーズのカタログには掲載されていない、
実際の施工事例を見てみましょう!
実際の施工事例①~冬期の断熱効果~

この結果がこちらです。
下記の表は「塗膜表面温度」のグラフです。
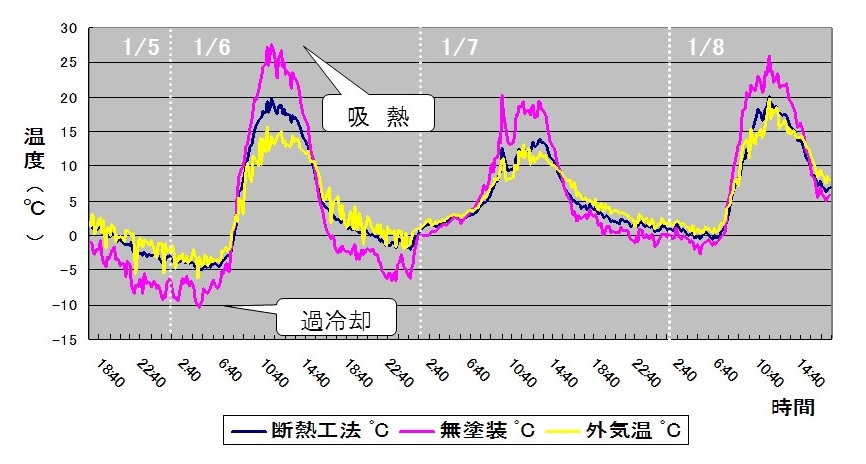
少々難しい表だが、断熱コートを塗装することにより、
夜間の過冷却、日中の吸熱を防止してくれることが分かります。
つまり
温度変化って、金属に非常に負荷を与えますからね。
さて、次の事例を見てみましょう。
実際の施工事例②~冬期の断熱効果~
<温度測定器(おんどとりTR-71U)>
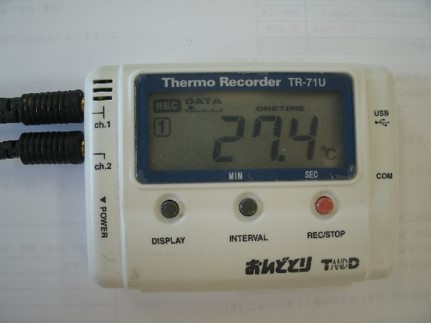
<守衛室内休憩室>

では、その結果を見てみましょう。
施工前後での温度変化
(冬場2018年12月21日~12月26日の午前4時で比較)
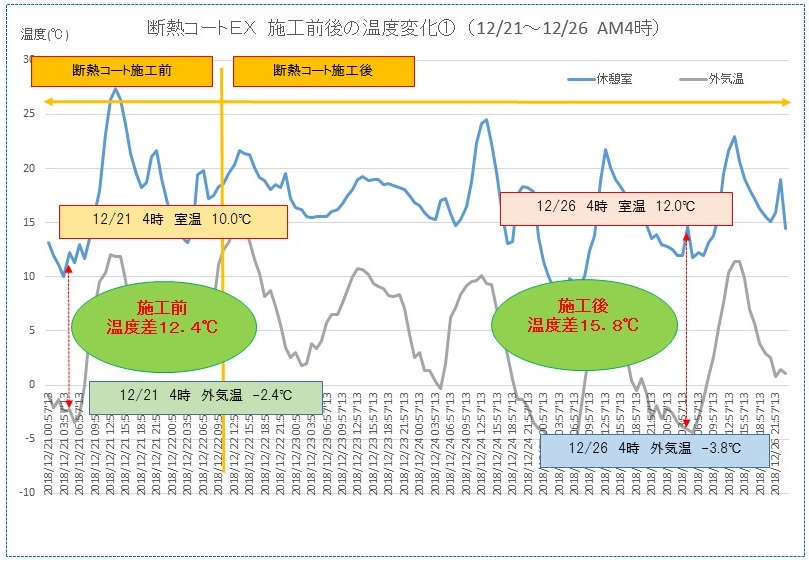
まとめると、
外気温が最も低くなる午前4時で比較した場合、
施工前に比べると、室温が高くなるという結果となり、
外気の影響を大きく受けずに室内温度が下がらず、
保温効果が向上していることが分かります。
つまり、断熱コートEXを施工することで、
冬場の部屋内の温度が下がりづらく、断熱効果が期待できる、
ということがわかります!
いかがでしたでしょうか?
断熱コートシリーズに、保温効果があるということが、
ご理解いただけたでしょうか?
断熱コートシリーズは、夏の暑さ対策だけではなく、
冬にも効果を発揮するんです!
先日、断熱コートの防水効果について、ご説明しましたが、
(詳しく知りたい方は、上記リンクからどうぞ!)
断熱コートシリーズ、非常に万能ですね!!
まだまだ寒さは続きそうです。
ぜひ、一度ご検討くださいね。
カタログのダウンロードはこちら!
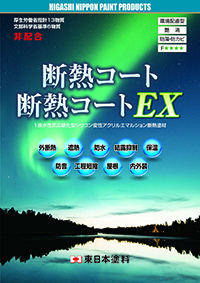
「より詳しく知りたい!」
「実際のカタログが欲しい」
「実際に現場を見てもらいたい!」
という方は、こちらから、お問合せくださいませ。
お問合せはこちら!
「断熱」
「夏涼しい!」
「省エネ!」
「部屋の中の温度が上がるのを防ぐ!」
「防音!」
「結露抑制!」
「白い!」
「厚み」
「あの独特な手触り!」(←?)
弊社内では、上記のような答えが返ってきました。
上記はすべて、断熱コートシリーズの特長を表しています。
しかし!
実は断熱コートシリーズには「保温性」という特長があるのをご存知ですか?
今日は、この「保温性」に着目して、説明していきますね。
「保温性」というと「冬」というイメージですが、
「結露抑制」と同様、冬期に効果を発揮するんです。
一般の塗料は、「温まりやすく冷めやすい」のですが、
断熱コートシリーズは、「温まりにくく冷めにくい」という特長があります。
これは、どういうことか、というと、
「温まりにくく冷めにくい」つまり「保温性が高い」ということになるんです。
「温まりにくいのに保温性?」
と思われる方もいらっしゃると思いますが、
サーモ機能付きの水筒を思い出してください。
「温かいものは温かいまま、冷たいもの冷たいまま」ですよね?
中の飲料などが同じ温度を維持する、ということになります。
これこそ、保温性なのです!
つまり、同じ温度を維持するということは保温効果が高い!ということなんです。
だからこそ、「温まりにくく冷めにくい」というのは
「保温性が高い」ということになります。
ここで、断熱コートシリーズのイメージ図を見てみましょう。
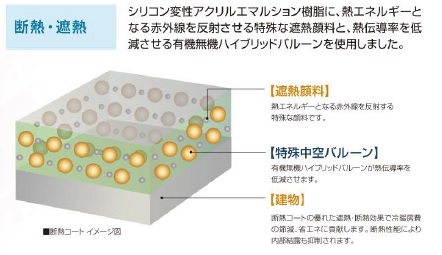
断熱コートシリーズには、「特殊中空バルーン」というものが使われています。
この「特殊中空バルーン」が、熱伝導率を低減させる働きをしています。
どういうことかというと、
このバルーンが熱を伝えない空気の層を作り、
この空気の層、つまり気泡が保温性を高めているのです。
この気泡の中の空気は温まると、その熱を保つ性質があります。
では、この「特殊中空バルーン」が入っている塗料と、
入っていない塗料では、どのくらい違うのでしょうか?
下記をご覧ください。
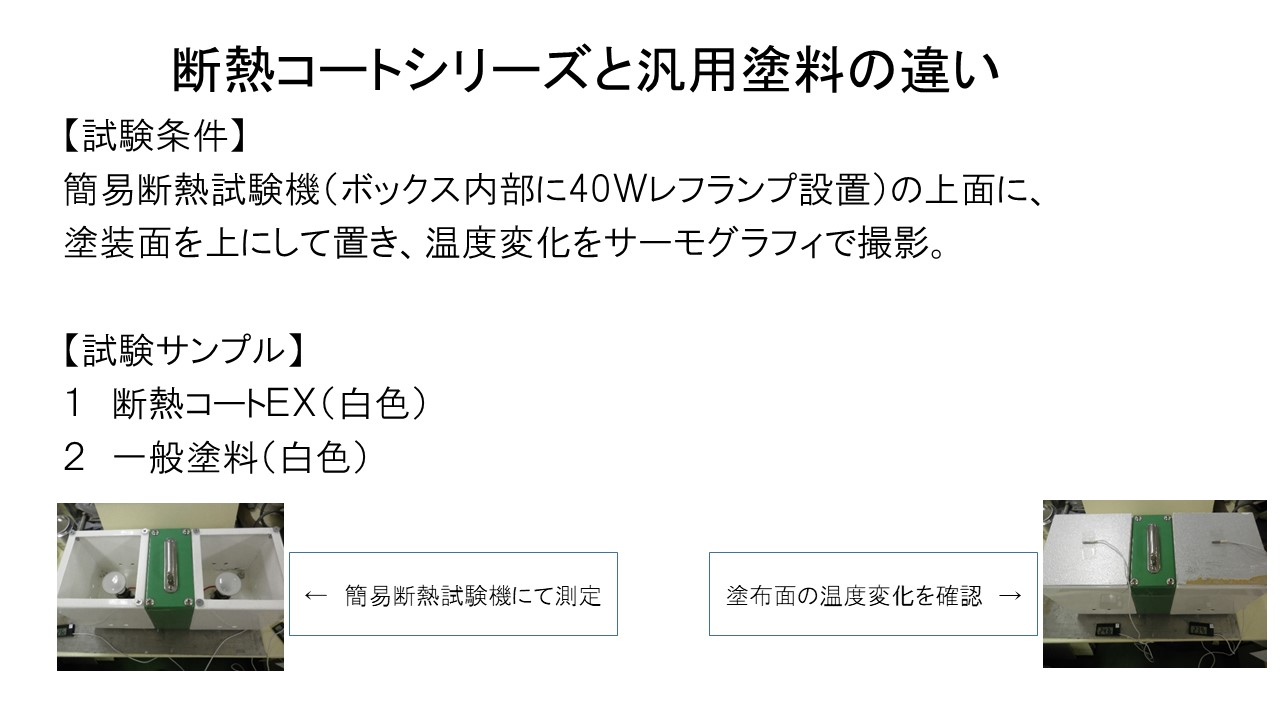
上記のような条件と装置で実験してみました。
すると、下記のような結果が得られました。
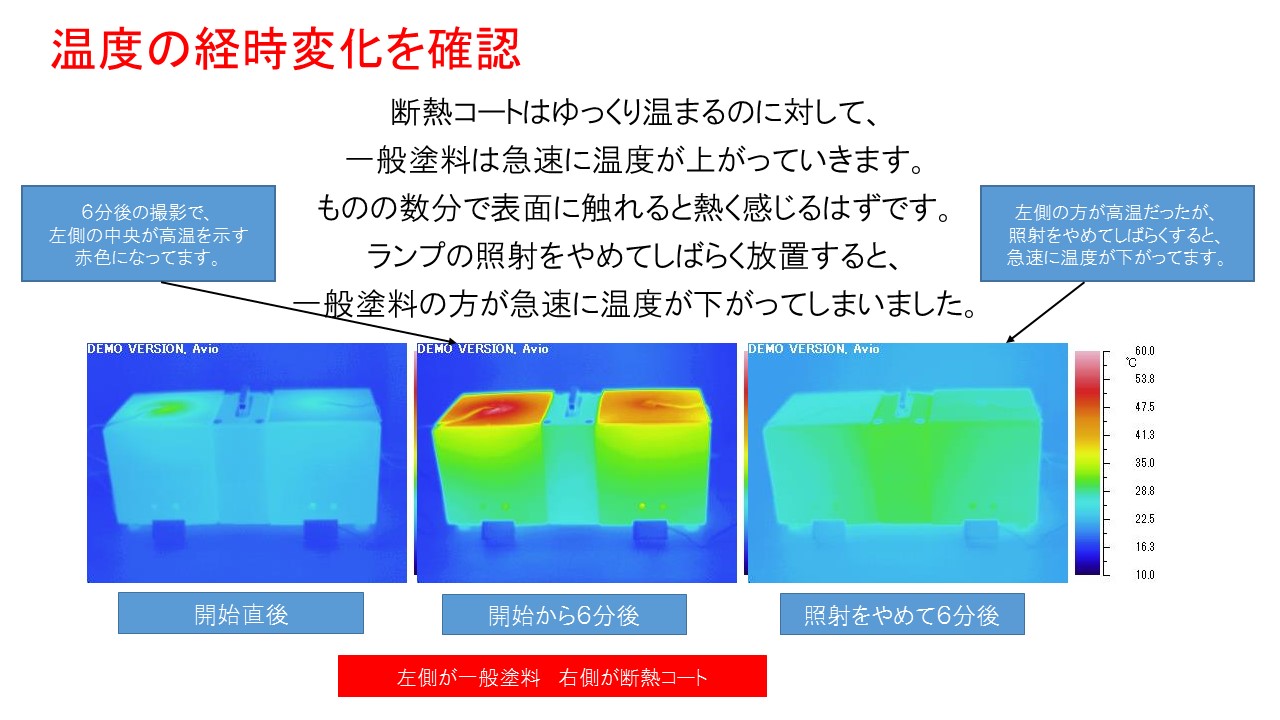
このことから、断熱コートEXを塗布したものは、ゆっくりと温まり、
ランプの照射をやめても、急激な温度低下が見られないということがわかります。
つまり、一般塗料と比較しても、「保温性が高い」ということが分かります。
「実験だけじゃなくて、実際はどうなの?」
と思われる方も多いと思います。
それでは、断熱コートシリーズのカタログには掲載されていない、
実際の施工事例を見てみましょう!
実際の施工事例①~冬期の断熱効果~

| 施工概要 | 折板屋根(約300㎡) |
| 仕様 | 遮熱サビ止めプライマー 0.16㎏/㎡ 断熱コート 0.7㎏/㎡ スーパートップ遮熱 0.3㎏/㎡ |
| 施工時期 | 2007年12月 |
| 測定条件 | 2008年1月5~8日の断熱施工面と無塗装折板面の塗膜表面温度を比較 |
この結果がこちらです。
下記の表は「塗膜表面温度」のグラフです。
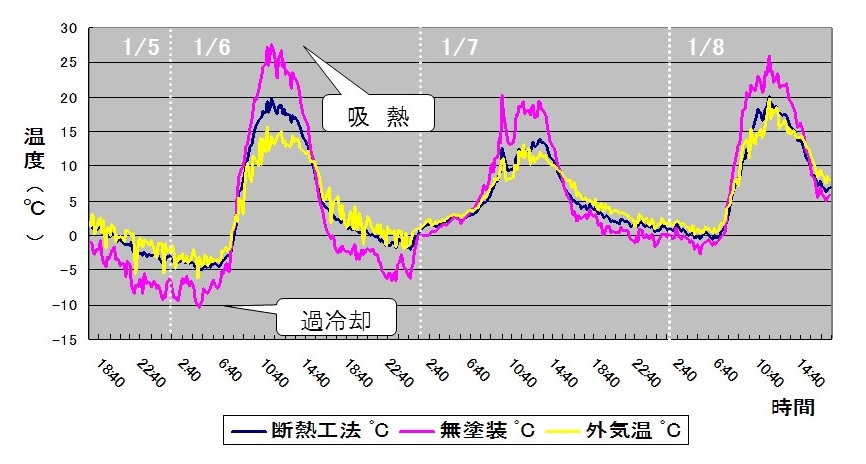
少々難しい表だが、断熱コートを塗装することにより、
夜間の過冷却、日中の吸熱を防止してくれることが分かります。
つまり
- 外気温による室内の温度変化軽減
- 金属疲労の防止
温度変化って、金属に非常に負荷を与えますからね。
さて、次の事例を見てみましょう。
実際の施工事例②~冬期の断熱効果~
| 施工概要 | 守衛室(外壁、鋼板屋根面) |
| 仕様 | 遮熱サビ止めプライマー 0.16㎏/㎡ 断熱コートEX 0.4㎏/㎡ 断熱コートEX 0.4㎏/㎡ (断熱コートEXは2回塗布) |
| 施工時期 | 2018年12月 |
| 測定期間 | 2018年12月~2019年1月 |
| 測定条件 | 守衛室内部に温度測定器(おんどとりTR-71U)を設置して、室内温度を測定 断熱コートEX施工前後の温度比較を行う ※ 測定器は、冷暖房の使用頻度が少ない休憩室に設置 |
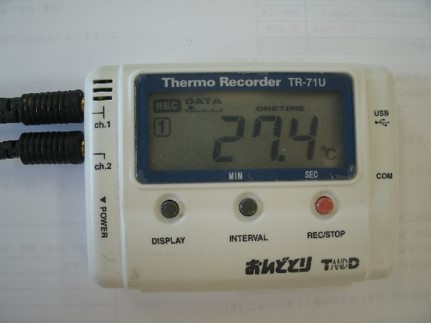
<守衛室内休憩室>

では、その結果を見てみましょう。
施工前後での温度変化
(冬場2018年12月21日~12月26日の午前4時で比較)
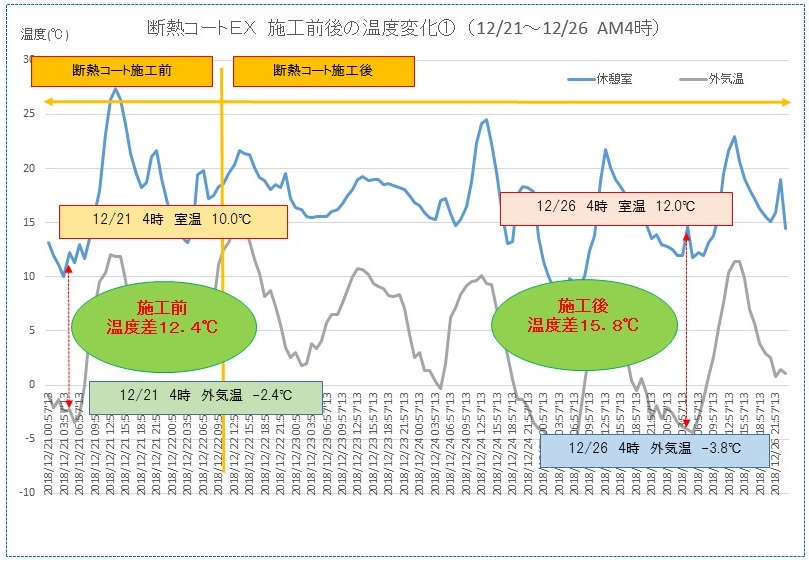
まとめると、
| 夜間 | 温度差 | 室内 | 外気温度 | 日時 |
| 施工前 | 12.4℃ | 10.0℃ | -2.4℃ | 2018/12/21 4時 |
| 施工後 | 16.8℃ | 12.0℃ | -3.8℃ | 2018/12/21 4時 |
施工前に比べると、室温が高くなるという結果となり、
外気の影響を大きく受けずに室内温度が下がらず、
保温効果が向上していることが分かります。
つまり、断熱コートEXを施工することで、
冬場の部屋内の温度が下がりづらく、断熱効果が期待できる、
ということがわかります!
いかがでしたでしょうか?
断熱コートシリーズに、保温効果があるということが、
ご理解いただけたでしょうか?
断熱コートシリーズは、夏の暑さ対策だけではなく、
冬にも効果を発揮するんです!
先日、断熱コートの防水効果について、ご説明しましたが、
(詳しく知りたい方は、上記リンクからどうぞ!)
断熱コートシリーズ、非常に万能ですね!!
まだまだ寒さは続きそうです。
ぜひ、一度ご検討くださいね。
カタログのダウンロードはこちら!
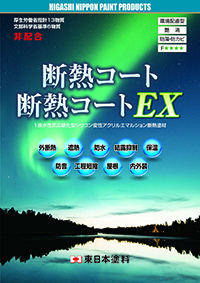
「より詳しく知りたい!」
「実際のカタログが欲しい」
「実際に現場を見てもらいたい!」
という方は、こちらから、お問合せくださいませ。
お問合せはこちら!

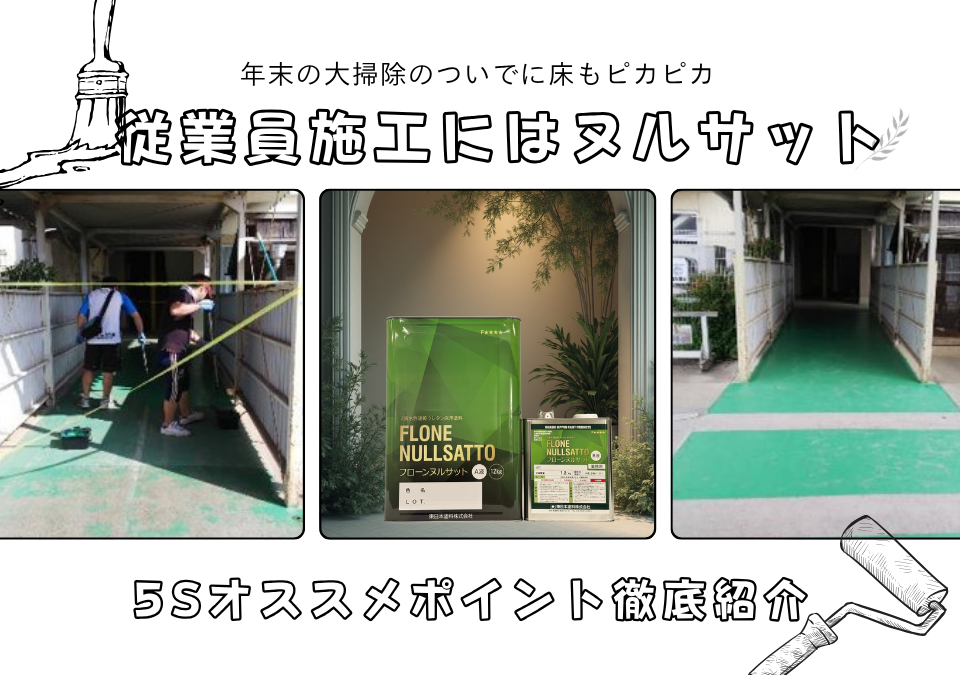

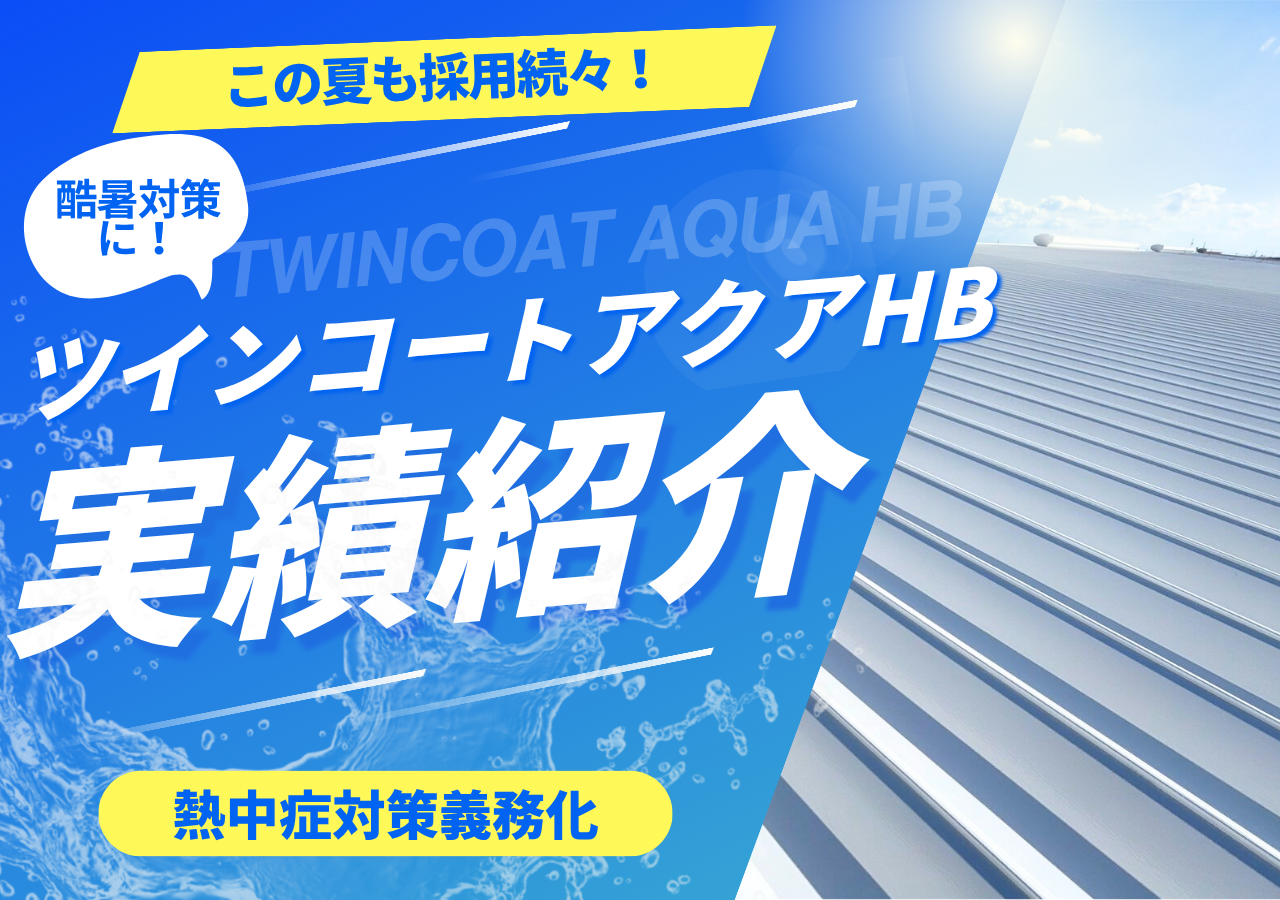
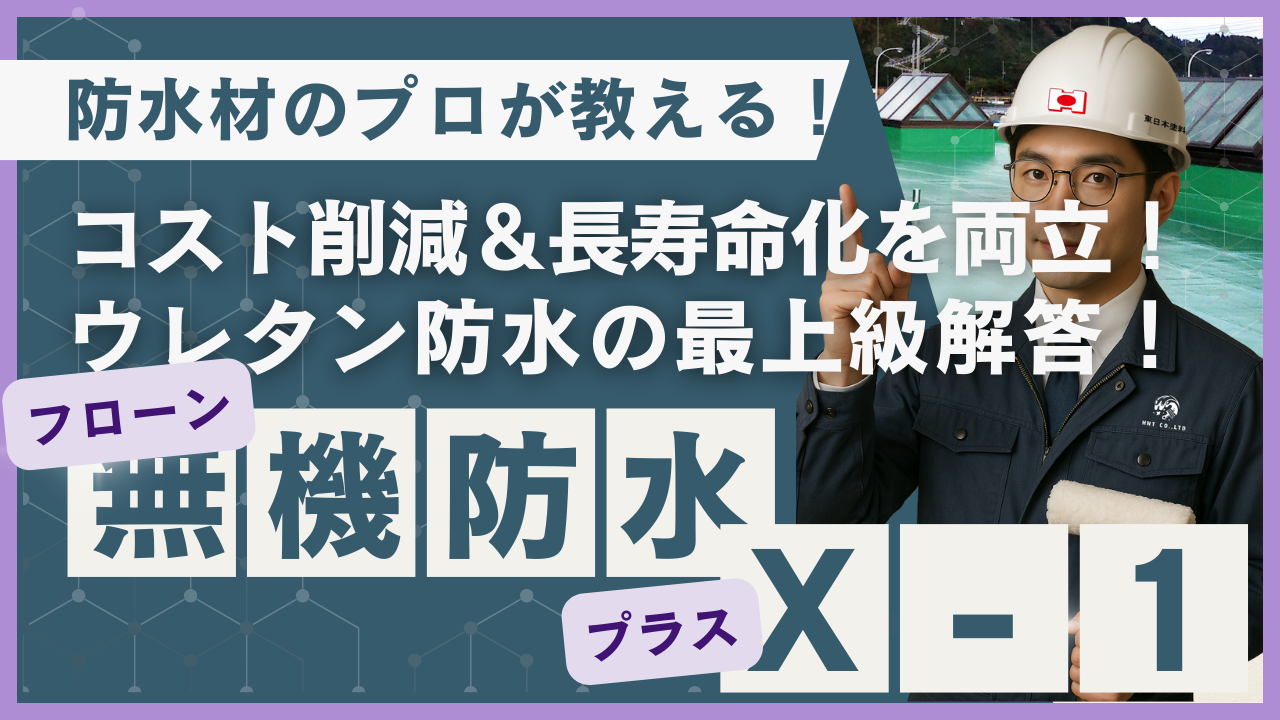
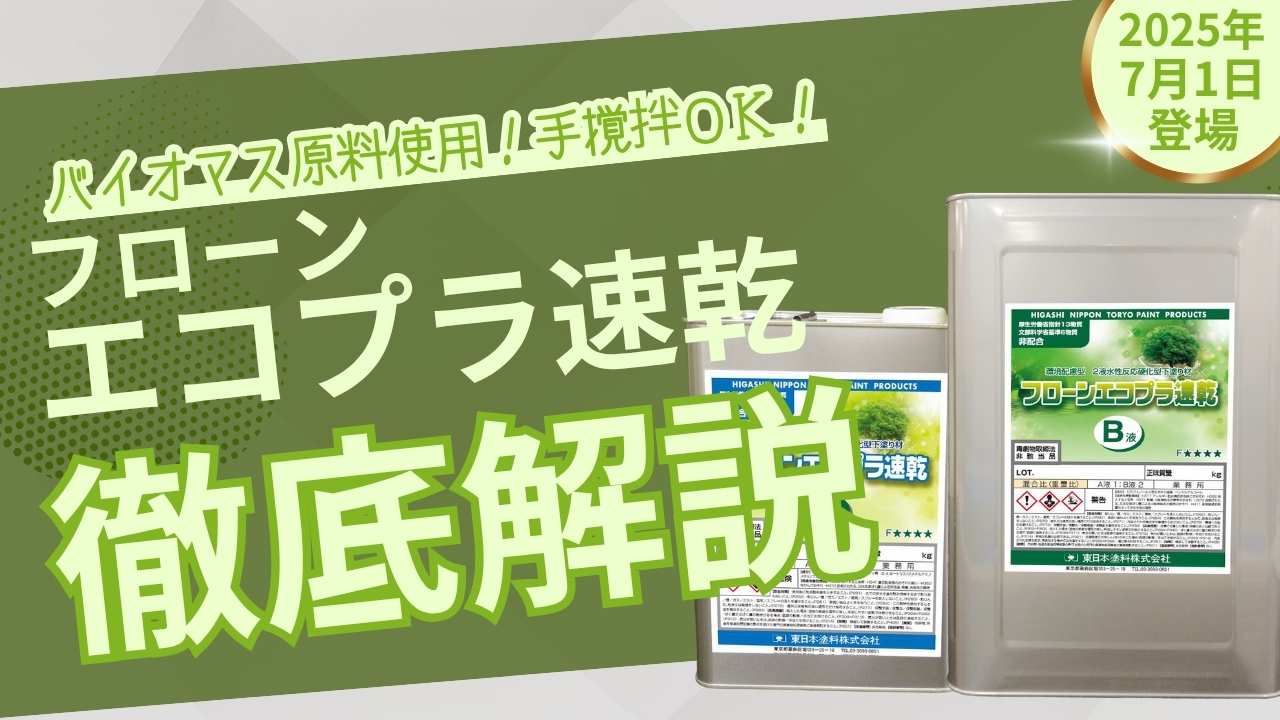
.jpg)